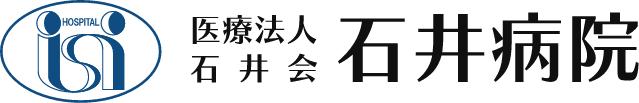炎症性腸疾患(IBD)は潰瘍性大腸炎とクローン病の2つの病気を指します。
厚生労働省の定める難病に指定されており、腸の粘膜に炎症を起こすことで下痢・腹痛・血便などの症状が現れます。
患者数は年々増加しており、10代から30代の比較的若い方で発症しやすいことが特徴ではありますが、最近では幅広い年代で発症する方も増えています。
はっきりとした原因は解明されていないこともあり、長期にわたる治療が必要となります。
炎症が長期化してくると消化管がんを発生することや、腸が狭窄してしまい手術を要することもあるため専門的な病院で治療を受けることが重要です。
炎症性腸疾患(IBD)とは?

● 潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis / UC)
潰瘍性大腸炎は、大腸の内側(粘膜)にびらんや潰瘍が生じる炎症性の病気です。
主な症状は、血便を伴う下痢や腹痛で、症状の程度には個人差があります。
炎症は通常、直腸から始まり、大腸の上部へと連続的に広がるのが特徴です。
現在、潰瘍性大腸炎を完全に治す薬はありませんが、炎症を抑えるための薬物療法は多く存在します。
治療の目的は、腸の炎症を鎮め、症状を軽減することで、日常生活への支障を最小限に抑えることです。
● クローン病(Crohn’s Disease / CD)
クローン病は、主に若年層に多くみられ、口から肛門までの消化管全域に炎症や潰瘍が生じる可能性がある炎症性の病気です。
特に、小腸の終末部と大腸・肛門に発症しやすく、病変が点在的(非連続的)にあらわれるのが特徴です。
主な症状には、腹痛、下痢、体重減少、発熱などがあり、症状は再燃と寛解を繰り返すことが多いです。
治療は主に薬物療法や栄養療法などの内科的治療が中心ですが、腸閉塞や穿孔、膿瘍といった合併症が生じた場合には、外科的治療が必要となることもあります。
検査
炎症性腸疾患(IBD)の診断には
「いつから症状がみられたのか」
「どの時間帯で症状が起きやすいか」
「おなか以外の症状はあるか」
など症状を詳しく教えていただくことが非常に重要です。
その上で血液検査、内視鏡検査、便検査など複数の検査を行い総合的かつ慎重に診断を行います。
診断後には定期的な血液検査や内視鏡検査で状態が悪化してきていないか確認することも重要になります。
当院では上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)、下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)に加えて小腸内視鏡検査(ダブルバルーン内視鏡検査)を行うことができます。
ダブルバルーン内視鏡検査は小腸を詳しく観察・治療するための検査です。クローン病では小腸に病変ができることも多いため、小腸検査を定期的に受ける必要がありますが通常の内視鏡では小腸の深部まで観察することができません。こちらは内視鏡に取り付けられた風船を閉じたり膨らませたりしながら小腸の奥まで内視鏡を進めていくことができます。
また、小腸に狭窄ができてしまった場合には適応に応じて内視鏡で拡張術を行うこともあります。

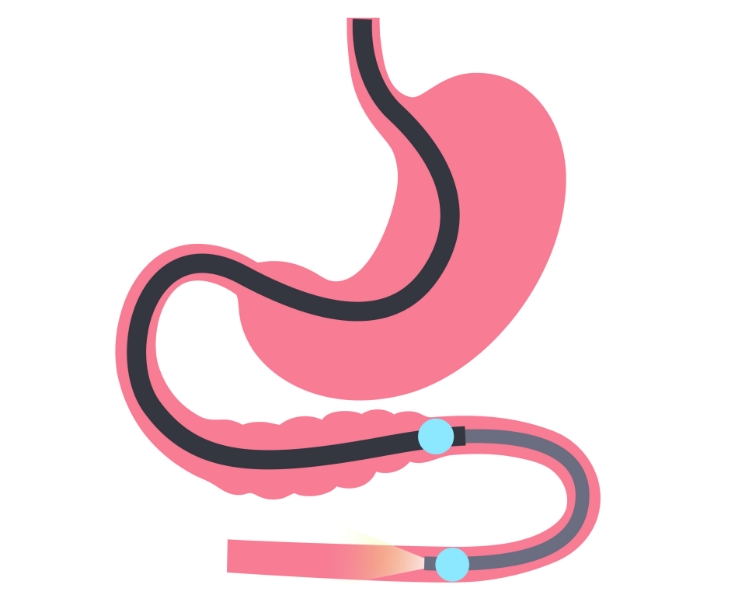
治療
炎症性腸疾患(IBD)の治療は主に薬物療法と食事療法が中心となります。
特にここ数年の薬物療法の進歩は目覚ましく、新しい治療薬が多く開発されています。
それにより病気と上手に付き合いながら日常生活を送れるようになってきています。
患者さんの状態に合わせて適切な治療を行えるよう、納得がいくまで説明した上で治療を進めていきます。

潰瘍性大腸炎・クローン病の内科的治療
● 栄養療法・食事療法
腸への負担を減らし、栄養状態を整えることは、症状の改善や腸の回復にとても重要です。
腹痛や下痢を和らげるため、腸を安静に保ちつつ、食事からの刺激を減らす目的で、「エレンタール」や「ラコール」などの栄養剤を使うことがあります。
症状が落ち着いていれば通常の食事も可能ですが、食事によって症状が悪化することもあるため、注意が必要です。
一般的には低脂肪・低残渣(繊維の少ない)食が推奨されますが、消化吸収の状況や病変の場所によって合う食事は人それぞれ異なります。
主治医や管理栄養士と相談しながら、自分に合った食事内容を見つけていくことが大切です。
● 5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤
腸の炎症を抑える薬で、軽度~中等度の潰瘍性大腸炎に対して効果があります。
代表的な薬には、従来のサラゾスルファピリジン(サラゾピリン)のほか、副作用を軽減した改良薬としてメサラジン(ペンタサ、アサコール、リアルダ)などがあります。
これらは内服薬や坐薬として使用され、下痢・下血・腹痛などの症状を抑え、再発予防にも役立ちます。
● 副腎皮質ステロイド薬
中等度から重度の炎症に対しては、プレドニゾロン(プレドニン)やブデソニドなどのステロイド薬を内服・点滴・浣腸などの形で使用します。
● 免疫調節薬
炎症を抑える免疫の働きをコントロールする薬です。
アザチオプリン(イムラン/アザニン)
6-メルカプトプリン(ロイケリン)※未承認
寛解状態の維持に効果的です。
● 生物学的製剤
中等症から重症例では、免疫の過剰反応を抑える注射薬が用いられます。
代表的な製剤には以下があります。
- ・インフリキシマブ(レミケード):8週ごとに点滴投与
- ・アダリムマブ(ヒュミラ):2週ごとに自己注射
- ・ゴリムマブ(シンポニー):4週ごとに自己注射
- ・ミリキズマブ(オンボー):4週ごとに自己注射
- ・リサンキズマブ(スキリージ):8週ごとに注射
- ・ウステキヌマブ(ステラーラ):12週ごとに注射
- ・ベドリズマブ(エンタイビオ):8週ごとに点滴もしくは2週ごとに自己注射
● JAK阻害剤、S1P受容体調節剤
中等症から重症例に使用する内服薬です。
代表的な製剤には以下があります。
- ・ウパダシチニブ(リンヴォック)
- ・トファシチニブ(ゼルヤンツ)
- ・フィルゴチニブ(ジセレカ)
- ・オザニモド(ゼポジア)
これらの薬で効果が得られない場合は外科的手術が検討されることになります。
炎症性腸疾患(IBD)の医療費助成
指定難病である炎症性腸疾患(IBD)は医療費助成を受けることができます。
医療費助成を受けるには各都道府県の保健所で申請を行い、
受給者証の交付を受ける必要があります。
しかし全ての方が交付を受けられるわけではありません。
ご自身が交付の対象になるかは担当医にお尋ねください。
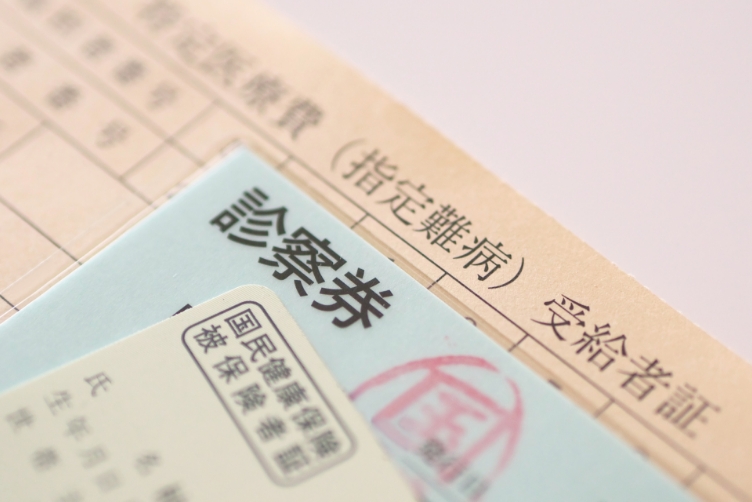
よくあるご質問|潰瘍性大腸炎
-
Q1.
潰瘍性大腸炎は治りますか?
-
A.
現在のところ、潰瘍性大腸炎を完全に治す治療法(完治)はありません。
ただし、適切な治療により炎症を抑え、症状が落ち着いた状態(寛解)を長く保つことは可能です。
-
Q2.
症状がよくなれば薬はやめてもいいですか?
-
A.
寛解期でも治療は継続することが大切です。
自己判断で薬を中断すると、再燃(再び症状が出ること)につながる恐れがあります。
中止は必ず主治医と相談してください。
-
Q3.
食べてはいけない物はありますか?
-
A.
症状が落ち着いているときは、基本的に制限のない食事が可能ですが、再燃を防ぐためには脂っこいものや刺激物は控えた方がよいとされています。
個人差があるため、主治医や栄養士と相談しながら調整しましょう。
-
Q4.
潰瘍性大腸炎はがんになりやすいのですか?
-
A.
長期間にわたり潰瘍性大腸炎にかかっている方は、大腸がんのリスクが高くなる可能性があります。
定期的な大腸内視鏡検査などで早期発見・対応が可能です。
-
Q5.
妊娠・出産に影響はありますか?
-
A.
症状が安定していれば妊娠・出産は十分に可能です。
ただし、服用している薬によっては注意が必要なものもあるため、計画的に主治医へ相談することが大切です。
よくあるご質問|クローン病
-
Q1.
クローン病は一生付き合っていく病気ですか?
-
A.
現在のところ、クローン病を完全に治す治療法(完治)はありません。
ただし適切な治療により炎症を抑え、症状が落ち着いた状態(寛解)を長く保つことは可能です。
-
Q2.
どのような食事に気をつければいいですか?
-
A.
食事は消化に優しく、脂肪の少ないものが基本です。
食事内容は病変の部位や症状の程度により異なります。再燃を防ぐためには、自分に合った食事を見つけることが重要です。
-
Q3.
運動の制限はありますか?
-
A.
炎症が落ち着いているときは、基本的に運動の制限はありません。
しかし貧血が強い時や栄養状態が悪い時などには注意が必要です。
-
Q4.
手術が必要になることはありますか?
-
A.
病状や合併症(腸閉塞、穿孔、膿瘍など)によっては、外科的な手術が必要になることもあります。
ただし、手術が治療のゴールではなく、内科治療とあわせて行うことで症状をコントロールします。
-
Q5.
クローン病は遺伝しますか?
-
A.
家族に患者さんがいる場合に発症リスクがやや高くなる傾向はありますが、必ず遺伝するというわけではありません。
発症には遺伝的要因に加え、環境や免疫の異常なども関係していると考えられています。
● 受診されるにあたって
すでに炎症性腸疾患の診断をなされている方も、お腹の症状で困っており炎症性腸疾患が心配な方もお気軽に当院を受診ください。
県内に数人しかいない炎症性腸疾患の専門医が診療を担当させていただきます。
不安なことや分からないことがある場合にも遠慮なく相談いただければと思います。
IBD診療担当医師 橋本悠
日本炎症性腸疾患学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、医学博士、炎症性腸疾患関連の論文を複数執筆。
2017年から横浜市立大学附属市民総合医療センター 炎症性腸疾患センターで勤務。
2019年に出身地である群馬へ戻り、炎症性腸疾患チームのリーダーとして診療・研究に従事。
2025年からは石井病院にて勤務し炎症性腸疾患の専門診療を担当。
外来担当医表はこちらからご確認ください。